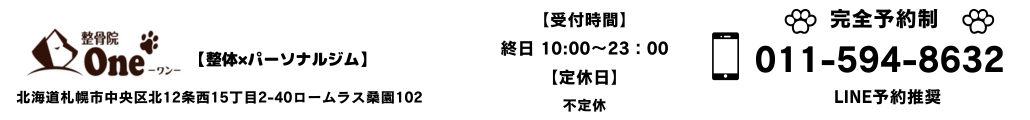炭水化物と体脂肪燃焼の関係性 〜ホルモンバランスの視点から〜
ダイエットにおいて「炭水化物を減らせば脂肪が燃える」という単純な考え方が広まっています。しかし、ホルモンバランスの視点から見ると、炭水化物は適切に摂取することで脂肪燃焼をサポートする重要な役割を果たします。本記事では、炭水化物と体脂肪燃焼の関係をホルモンの観点から解説します。
1. インスリンと脂肪燃焼の関係
炭水化物を摂取すると血糖値が上昇し、それに伴いインスリンが分泌されます。インスリンは血糖を細胞に取り込む役割を持ちますが、脂肪の蓄積を促すホルモンでもあります。そのため、「インスリンが分泌されると脂肪が燃えにくくなる」と考えられがちです。
しかし、インスリンには筋肉の合成を促進する働きもあり、適度な分泌はトレーニング後の回復や筋肉維持に重要です。極端にインスリンを抑えると、筋肉が分解されやすくなり、基礎代謝の低下につながります。
適切なインスリン管理のポイント
炭水化物はトレーニング前後に摂取することで、脂肪蓄積を抑えつつエネルギー補給が可能
低GI(グリセミック・インデックス)の炭水化物(玄米、オートミール、全粒粉など)を選ぶことで、血糖値の急上昇を防ぐ
極端な糖質制限は筋肉分解を促進し、代謝低下を招くため注意
2. レプチンと代謝維持
レプチンは「満腹ホルモン」とも呼ばれ、食欲の抑制や代謝の調整に関与するホルモンです。ダイエットで長期間低炭水化物の状態が続くと、レプチンの分泌が減少し、
食欲が増す
代謝が低下する
停滞期に入りやすくなる といった問題が起こります。
レプチンを維持するポイント
週に1〜2回「リフィードデイ」を設け、炭水化物を増やすことでレプチンの分泌を維持
極端な糖質カットではなく、適量を確保する
3. コルチゾールと脂肪燃焼
コルチゾール(ストレスホルモン)は、長期間の糖質制限や過度なカロリー制限で上昇しやすくなります。コルチゾールが高くなると、
筋肉分解が進む
体脂肪が蓄積しやすくなる
睡眠の質が低下する などの悪影響が出ます。
コルチゾールをコントロールするポイント
1日3〜4回、安定した炭水化物摂取で血糖値を一定に保つ
睡眠をしっかりとり、ストレスを管理する
極端な低炭水化物ダイエットを避け、ホルモンバランスを崩さない
4. グルカゴンと脂肪燃焼の促進
グルカゴンは、インスリンとは逆に脂肪燃焼を促進するホルモンです。炭水化物を適度に制限するとグルカゴンが分泌され、脂肪がエネルギーとして利用されやすくなります。しかし、完全な糖質カットではなく、適度な摂取がポイントです。
グルカゴンの分泌を促す方法
低〜中程度の炭水化物摂取でバランスを取る
高タンパク食を意識し、筋肉を維持
5. まとめ
炭水化物は適切に摂取することで、ホルモンバランスを整え、脂肪燃焼を促進することが可能です。極端な糖質制限は代謝の低下や筋肉分解を招くため、
低GIの炭水化物を選ぶ
トレーニング前後に適切な糖質を摂取する
リフィードデイを活用し、レプチンを維持する
ストレス管理を行い、コルチゾールの上昇を防ぐ
といった工夫が重要です。ダイエット成功のためには、単に糖質を減らすのではなく、ホルモンの働きを理解し、最適なバランスを見つけることが大切です。
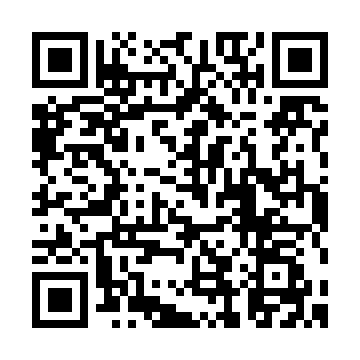 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →