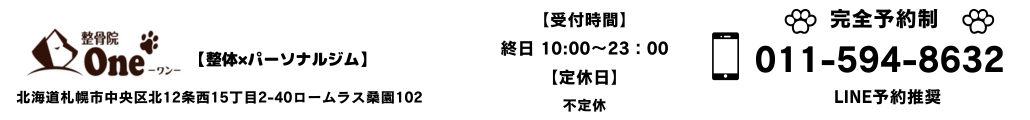健康に悪い」を盾にする人たちへ——ダイエット指導者が抱えるリスクと対策
ダイエット指導において「健康被害」は避けるべきものです。
それは間違いありません。
むしろ、健康を土台にしていない指導は、もはや指導ではありません。
でも一方で、「健康に悪いから」と言われた瞬間、
すべての正当性がかき消される場面に、現場の指導者は直面することがあります。
「健康」という絶対正義
たとえば、こう言われたとします。
「トレーナーに言われて糖質制限したら、体調を崩しました」
「疲労が抜けない。ホルモンバランスが崩れたかもしれない」
「月経が止まりました。これは健康被害では?」
このような声が上がった瞬間、
内容がどうであれ、指導者側が“加害者”の立場に立たされてしまうことがあります。
そこに意図的な悪意がなかったとしても、
「健康」はあまりにも強力なワードであり、それを盾にされたら、
ほとんどの反論は“言い訳”として処理されてしまうのです。
指導者が向き合うべき2つのリスク
1つは実際に健康を害するような誤った指導を行ってしまうリスク。
もう1つは、正しい指導をしても、主観的な「体調の不調」が“被害”として訴えられるリスク。
後者の方が、実は厄介です。
たとえば、
・糖質制限を正しく行っても、ケトーシスに入るまでの間は体調不良を感じやすい
・体力不足や月経トラブルは、栄養以外の生活要因でも起こる
・「やりすぎ」「独断の制限」などが介入していた可能性もある
このような背景があっても、「被害」として訴えられると、
外から見れば「トレーナーのミス」でしかありません。
対策:健康の“見える化”とガイドラインの明文化
では、どう守るか。
1. 初回説明で「健康とダイエットの両立」を明確に伝える
「体調に異変があれば、すぐ報告してください」
「極端な制限はしません。続かないやり方は意味がありません」
このような“安全基準”を明確にすることで、
「最初に言ってたことと違う」という誤解を防ぎます。
2. 体調チェックと共有ログの徹底
・睡眠
・月経
・エネルギー感(疲労)
などの主観的データも、記録として残すことで、
「どこで無理がかかったか」が共有されやすくなります。
最後に
本当に健康を守るために必要なのは、
「制限」よりも「対話」です。
ダイエット指導は時に、
食事や運動よりも“信頼関係”が結果を左右します。
そして信頼とは、
お互いが「相手のせいにしない」ことから生まれます。
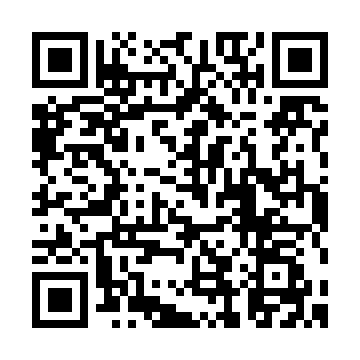 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →