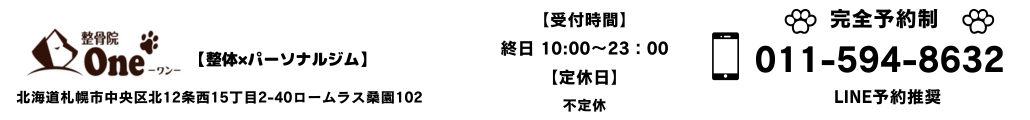ダイエットが停滞する本当の理由
―感覚ではなく“数値”で見直すべき科学的な根拠と、正しい自己分析のやり方―
はじめに
「頑張っているのに体重が減らない」 「食べすぎている自覚はないのに痩せない」 こうした悩みは、ダイエットをしている多くの人が抱える問題です。実際、指導現場でもこれらの声は頻繁に耳にします。
その原因の一つが、「感覚」に頼りすぎていることです。自分の行動を正確に把握できていないため、無駄な努力を繰り返している場合が多いのです。
今回は、なぜ「感覚」だけではダイエットがうまくいかないのか、そしてどうすれば「数値」を使って正しく自己分析できるのかを解説します。科学的な根拠をもとに、実践的な方法をお伝えしますので、これを参考にしてダイエットを成功に導きましょう。
なぜ「感覚」に頼るとダイエットはうまくいかないのか?
1. 脳と行動のギャップ
私たちの脳は、自分の摂取カロリーや消費カロリーを正確に把握することができません。この事実は、数々の研究で証明されています。
例えば、アメリカ・コーネル大学のBrian Wansink教授の研究によると、人間は自分が食べたカロリーを平均して20~40%過少に見積もる傾向があることがわかっています(Wansink et al., 2004)。特に「健康的な食事をしている」と思っていると、その感覚がさらに強まる傾向があります。
同様に、運動による消費カロリーを過大評価してしまうこともあります。例えば、30分のウォーキングで実際には150kcal程度しか消費していないのに、300kcal以上だと思い込んでしまうこともあります(Lichtman et al., 1992)。
このように、感覚だけで判断すると、実際には過剰に食べていたり、運動の効果を過信してしまったりするのです。
「数値化」=現状の見える化
ダイエットを成功させるための第一歩は、「自分の行動」を数値化して把握することです。これにより、感覚に頼らずに客観的に現状を理解することができます。
【実践編】正しく現状を把握するための「記録すべき項目」と方法
数値化を始めるための具体的な方法を紹介します。これらはすぐに実践できる方法ばかりですので、今すぐにでも取り入れてみてください。
1. カロリーとPFC(タンパク質・脂質・炭水化物)を記録する
推奨ツール:
あすけん
MyFitnessPal
カロミル
食べたもののカロリーだけでなく、PFC(タンパク質、脂質、炭水化物)のバランスも記録します。特に、ダイエット中に重要なのはタンパク質の摂取です。筋肉量の維持や代謝を保つために、体重1kgあたり1.2〜1.6gのタンパク質を目指しましょう(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)。
2. 運動の頻度・時間・強度を記録する
推奨方法:
トレーニング内容(例:スクワット60kg×8回×3セット)
有酸素運動なら、時間+心拍数(130~140bpmで30分)や歩数を記録
スマートウォッチやヘルスアプリを活用してもOK。運動は、週150分以上の中強度の身体活動(速歩や軽いジョギング)が推奨されています(厚生労働省「身体活動基準2013」)。
3. 毎日の体調・生活データを記録する
推奨項目:
体重(毎朝同じ条件で計測)
睡眠時間
起床時の体調(疲労感、寝起きの質など)
トイレ(便通の有無やリズム)
これらのデータを記録することで、「体調が崩れやすい日」や「停滞している時期に共通する生活習慣」が見えてきます。
数値化がダイエットを成功に導く理由
1. 思い込みから脱却できる
「食べていないつもりだったけど、実は結構食べていた」 「運動しているつもりだったけど、実際は足りていなかった」
数値化することで、こうした認知のズレに気づくことができます。そのズレを修正することで、効率的に改善策を見つけ出すことが可能になります。
2. 習慣と結果の因果関係が見える
「食事」「運動」「体調」のデータをつなげることで、自分の行動と結果の関係が明確にわかります。これにより、「やった分だけ結果が出る」という実感を得られるので、モチベーションも維持しやすくなります。
まとめ:行動が変われば、結果は変わる
ダイエットがうまくいかない原因は、実は「自分がサボっているから」ではなく、「何が足りないのか、どこにズレがあるのか」を把握できていないことが多いのです。
「感覚」に頼らず、「数値」に基づいて現状を見直せば、何をすべきかが明確になり、あなた専用の成功ルートが見えてきます。正しい自己分析を行い、データに基づいて改善策を講じることで、リバウンドしにくい体作りができるようになります。
今日から早速、記録を始めて、あなたのダイエットを科学的に管理しましょう。
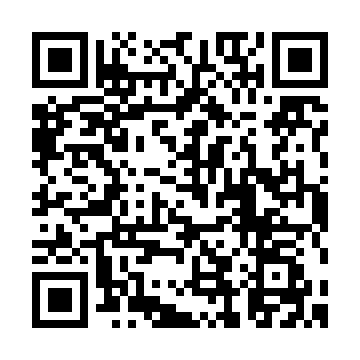 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →