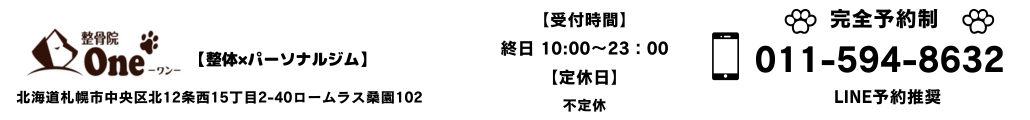さて、ダイエットや健康といえば「鶏むね肉」が鉄板ですが、
実は“魚”には肉にない魅力がたくさんあります。
今回は、「魚=高タンパク・低脂質」だけでは語りきれない
その“意外な栄養効果”について掘り下げてみます。
タンパク質は“種類”と“吸収”で差がつく
まず、魚のタンパク質は「消化吸収が速い」ことが大きな特徴です。
特に白身魚(タラ、カレイ、タイなど)は胃腸への負担が少なく、
トレーニング後や食欲の落ちる減量期にも向いています。
加えて、魚のタンパク質には「必須アミノ酸」がバランスよく含まれており、
体づくりの観点からも非常に優秀です。
魚の脂質は“悪者”ではない
脂質=太ると思われがちですが、魚の脂は例外です。
特にサバ・サンマ・イワシなどの青魚には
EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富に含まれています。
これらは「オメガ3脂肪酸」と呼ばれる、抗炎症・血流改善・脳機能サポートなど
“体の中で炎症を鎮める”働きがある良質な脂質です。
・疲れやすい
・肌荒れしやすい
・集中力が続かない
・慢性的な肩こり・腰痛がある
こうした症状がある人は、魚の脂を摂ることで改善する可能性があります。
魚には“ビタミンD”という見逃せない栄養素も
ビタミンDは、骨の強化や免疫力に関与する栄養素ですが、
現代人は慢性的に不足しがちです。
特に日光に当たる時間が少ない人、屋内仕事の人は
「魚を食べること」がビタミンD補給の有効な手段になります。
また、ビタミンDは筋肉の合成やテストステロンにも関与しているため、
「魚を食べる=筋肉が増えやすい身体環境に近づく」とも言えます。
魚を食べることは“自律神経の安定”にもつながる
オメガ3系脂肪酸の働きで副交感神経が優位になりやすくなります。
これは「リラックスしやすくなる」ということ。
つまり、魚は「栄養面」だけでなく「自律神経」にも働きかける食品です。
睡眠の質が悪い
疲れが抜けない
落ち着かない
そんな方にも、魚はおすすめの選択肢になります。
それでも魚が面倒だという人へ
わかります。
焼くとにおいが出る、骨がある、保存が効かない。
だからこそ、現代には「缶詰」「冷凍」「真空パック」など
便利な加工品もたくさん出ています。
・サバ缶(水煮 or 味噌煮)
・ツナ缶(ノンオイル)
・鮭フレーク(無添加)
・冷凍の切り身魚(グリルなしでもOK)
こうした商品をうまく活用すれば、
魚はもっと身近になります。
最後に
魚は「体にいい」とよく言われますが、
その意味を知ることで、選択の価値が深まります。
単なる“カロリー制限”ではなく、
“体が整う方向に導く食事”として魚を見てみる。
それができれば、
食事はもっと“結果につながる”行為になります。
整った体は、整った食事から。
今日の一食に、魚を選んでみてください。
公式LINE
https://lin.ee/O8uK5K
有料note
https://note.com/kazu20271803
X(旧Twitter)
https://twitter.com/OneOneStep1
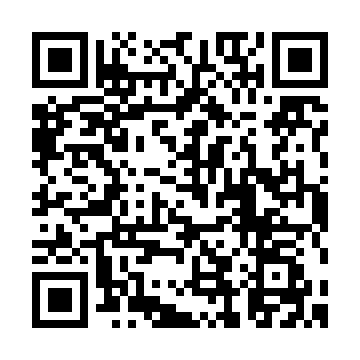 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →