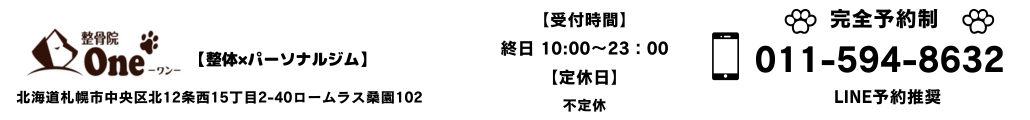家庭の食卓文化とメンタルの深いつながり
― なぜ“誰と食べるか”が、心を整えるのか ―
こんにちは、犬山和也です。
ご飯をひと口食べた瞬間に「なんかホッとした…」って思ったこと、ありませんか?
僕はカレーライスと白菜の味噌汁で、それを毎回やってます。
食事というと、「何をどれだけ食べたか」「栄養バランスは?」といった“機能面”ばかりが語られがちです。
でも、もうひとつ忘れてはいけないのが 「どこで・誰と・どう食べるか」 という“文化面”です。
その中でも、家庭の食卓文化は、僕たちの心に思っている以上に深く関わっています。
「食卓」は、感情と記憶の交差点
人は、記憶と感情を結びつけるときに「匂い」と「味覚」を強く使います。
・誕生日のちらし寿司
・試験前夜のインスタントラーメン
・帰省した時のあったかい味噌汁
こうした記憶って、意外と鮮明に残っていたりします。
それは、“食事”という行為が、感情と一緒に刻まれているからです。
食卓は、家庭の“安心基地”
家族で囲む食卓には、言葉にならない安心感があります。
沈黙があってもいい
多少ケンカしていても座る場所がある
黙ってご飯を出してくれる人がいる
これは、自分がここにいてもいいと思える感覚をつくる、ひとつの基盤です。
それが日々のメンタルを支える「土台」となります。
現代社会で食卓が崩れていく現実
忙しさ、スマホ、共働き、個食化。
家庭の食卓は、少しずつ“時間”としても“空間”としても失われつつあります。
特に子どもや思春期の段階で「誰かと一緒に食べる経験」が少ないと、
自己肯定感の形成にも影響があることがわかっています。
「栄養だけ整っていればいい」は本当か?
例えば、栄養バランスは完璧でも、
誰とも話さず、孤独に食べる日々が続いたら…
それは本当に“健康的”といえるでしょうか?
食事は、栄養素の補給だけではなく
感情を落ち着け、自己を回復させる行為でもあります。
「1日1回だけでも一緒に食べる」
「作ってくれた人に“ありがとう”を伝える」
「食卓に花を飾ってみる」
そんな小さな文化が、心の安定につながります。
僕たちは“食べる”ことで支え合っている
メンタル不調の背景には、「孤独」や「自律神経の乱れ」など、複合的な要因があります。
そのなかで、“食卓”という場所がもつ癒しの力は、もっと見直されるべきだと感じています。
人は誰かと「一緒に食べる」ことで、孤独感が和らぎ、緊張がほぐれます。
それが結果として、「睡眠の質」や「体調の安定」にまでつながるのです。
最後に
ダイエットや健康を語るとき、
「何を食べるか」「どう食べるか」はとても大切です。
でもそれと同じくらい、
**「誰と食べるか」や「食卓にどんな空気が流れているか」**も、大切にしてほしいと思います。
食卓には、栄養を超えた“人とのつながり”がある。
それを感じられるだけで、毎日のご飯が少しだけ特別な時間になります。
公式LINE
https://lin.ee/O8uK5K
有料note
https://note.com/kazu20271803
X(旧Twitter)
https://twitter.com/OneOneStep1
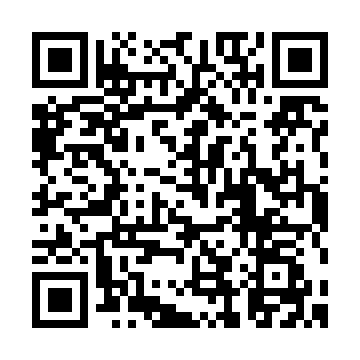 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →