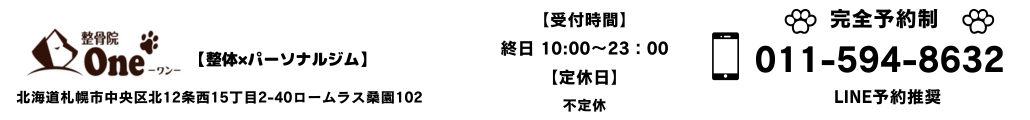食品添加物について学ぶ
〜正しく理解して、賢く選ぶ〜
1章 食品添加物とは何か?
食品添加物とは、食品を加工・保存・風味づけするために使われる物質の総称です。
大きく分けると以下のような役割があります。
保存料(腐敗やカビを防ぐ)
着色料(見た目を鮮やかにする)
甘味料(砂糖の代わりに甘みをつける)
乳化剤(油と水を混ぜやすくする)
香料(風味を加える)
つまり「食品を長持ちさせ、安全に届ける」「食べやすくする」という目的で使われています。
2章 安全性はどう担保されている?
日本で食品添加物として使用される物質は、厚生労働省による厳しい審査を経ています。
動物実験や臨床研究で毒性・発がん性などをチェック
一日の摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)が設定
その基準を大きく下回る量でのみ使用可能
つまり「使える量」「使い方」は厳密に決められており、基準内で使う限り健康に影響はないとされています。
3章 よくある誤解
「添加物=体に悪い」
→ 実際は自然由来のもの(ビタミンCやレシチンなど)も多いです。「海外で禁止されている=危険」
→ 国ごとに食文化や摂取量が違うため、基準も異なります。日本で禁止されていて海外でOKな物質もその逆もあります。「無添加=絶対に安全」
→ 無添加でも食中毒リスクはあります。保存料が入っていない分、管理が悪ければ逆に危険な場合も。
4章 リスクと向き合う
ただし、食品添加物には「ゼロリスク」ではない側面もあります。
長期的に大量摂取した場合の影響は完全には不明
複数の添加物を組み合わせた場合の相互作用は研究途上
一部の人にはアレルギーや過敏反応を起こすこともある
そのため「使うのは安全だが、必要以上に摂る意味はない」というのが実際です。
5章 現実的な付き合い方
加工食品に偏らず、基本は生鮮食品を中心に
無添加にこだわる必要はないが「毎日大量に」は避ける
食品表示を見て、何がどのくらい入っているか確認する習慣を持つ
つまり、**“避ける”ではなく“理解して選ぶ”**ことが大切です。
まとめ
食品添加物は「便利さと安全性を両立させる仕組み」です。
適切な範囲で使われている限り、健康リスクは非常に低い
無添加=絶対安全ではなく、リスクは保存や管理の方にある
正しく理解し、日常の食生活で「過剰に頼らない」ことが現実的な選択肢
食事を整える上で大切なのは「添加物を避ける」ことよりも「栄養バランスと食習慣」です。
【公式LINE】https://lin.ee/O8uK5K
【有料note】https://note.com/kazu20271803
【Xアカウント】https://twitter.com/OneOneStep1
【YouTube】https://www.youtube.com/@one2027
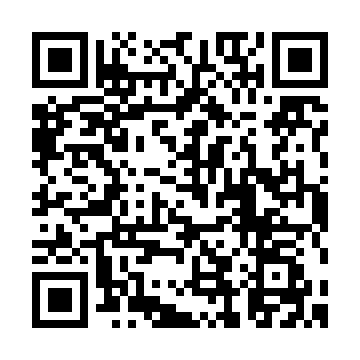 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →