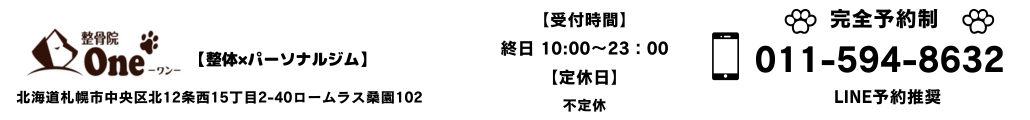栄養バランスは色合いで整える
〜カラフルな食卓が健康をつくる〜
1章 なぜ色で考えると良いのか?
栄養素を細かく計算するのは専門家でも大変です。
しかし「色」を基準にすると、自然とバランスが整います。
なぜなら、野菜や果物に含まれる色素(フィトケミカル)は、それぞれ異なる栄養素や抗酸化作用を持っているからです。
2章 色ごとの代表的な栄養素
赤色(トマト、パプリカ、イチゴなど)
リコピン、ビタミンC → 抗酸化作用・血流改善緑色(ほうれん草、ブロッコリー、キウイなど)
葉酸、クロロフィル、鉄分 → 造血・代謝サポート黄色・橙色(にんじん、かぼちゃ、柑橘類など)
βカロテン、ビタミンE → 免疫強化・皮膚の健康紫色(ナス、紫キャベツ、ブルーベリーなど)
アントシアニン → 眼精疲労・血管保護白色(大根、玉ねぎ、にんにく、きのこなど)
イソアリシン、食物繊維 → 免疫力・消化サポート
3章 実践しやすい工夫
食卓を見たときに「3色以上」が揃っているかをチェック
お弁当やプレート料理なら「信号色(赤・黄・緑)」を必ず入れる
主菜は「茶色(肉や魚)」、副菜は「色とりどりの野菜」で構成するとバランスが良い
4章 1日の食事例
【朝食】
オムレツ(卵+ほうれん草+トマト)
オレンジ
【昼食】
鮭の塩焼き
かぼちゃの煮物
ブロッコリーとパプリカのサラダ
【夕食】
鶏むね肉のグリル
ナスとピーマンの炒め物
大根ときのこの味噌汁
見た目がカラフルになると、自然と栄養バランスも整います。
まとめ
栄養バランスを意識するなら、難しい計算をする必要はありません。
色の多さ=栄養素の多様性
1食で3色以上を目指す
旬の野菜や果物を取り入れる
「カラフルな食卓」が、そのまま「健康な体」をつくる近道になります。
【公式LINE】https://lin.ee/O8uK5K
【有料note】https://note.com/kazu20271803
【Xアカウント】https://twitter.com/OneOneStep1
【YouTube】https://www.youtube.com/@one2027
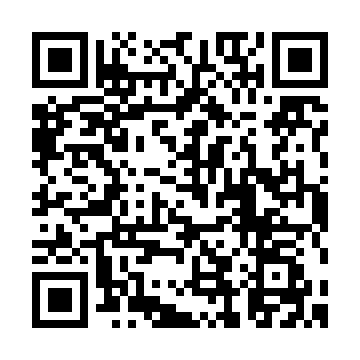 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →