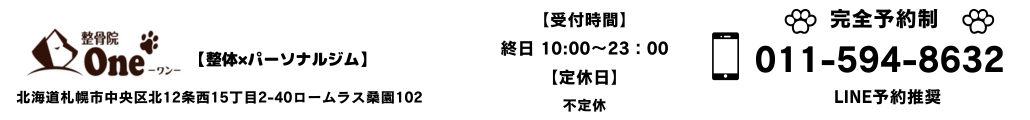正しいより「自分に合っている」食事を見つけよう
〜体が答えを知っている〜
SNSを開けば、「糖質は悪」「〇〇を食べると痩せる」など、
健康やダイエットに関する情報があふれています。
でも、その“正しさ”はあなたにとっての正解でしょうか?
食事も運動も、誰かの成功法則をコピーするだけでは長続きしません。
必要なのは、「自分に合っているか」を見極める視点です。
1章 “正しい”情報が“あなたに合う”とは限らない
どれだけ科学的でも、どれだけ流行っていても、
「合わないもの」は続けられません。
同じ食事法でも、
・朝食を抜くと調子がいい人
・朝ごはんを食べないと力が出ない人
がいます。
つまり「正しい情報」は存在しても、
“万人に合う情報”は存在しないのです。
2章 自分に合っているかを見極める3つのポイント
食べたあとに体調がどう変わるか
食後に眠くなったり、胃が重いと感じたら、
糖質・脂質のバランスや消化負担が合っていないサインです。翌朝の目覚めや便通がどうか
前日の食事は、翌朝に“結果”として出ます。
スッキリ起きられるか、便通が自然かどうか。これが最もリアルな健康指標。続けられるかどうか
一時的に体重が落ちても、我慢や制限でストレスが溜まる方法は続きません。
継続できる=自分に合っているのです。
3章 「体の声」を聞くということ
現代人は「思考」に偏りがちですが、
食事は“感覚”が教えてくれることのほうが多い。
・なんとなく疲れやすい
・甘いものを無性に欲する
・食後に集中力が切れる
これらは、栄養バランスのサインです。
数字や理論よりも、まず体の反応を観察することから始めましょう。
4章 食事はデータよりも実感
アプリやAIが「PFCバランス」を管理してくれる時代ですが、
本当に大切なのはデータを体感に変えること。
たとえば同じ糖質量でも、
白米とオートミールでは体の反応が違うように、
栄養の吸収や代謝は人によって変わります。
“自分の体で実験する”という意識が、
最も信頼できる「健康の教科書」になります。
5章 「合う食事」は探すものではなく、育てるもの
あなたの生活、仕事、ストレス、睡眠リズム。
それらが変われば、「合う食事」も変わります。
だからこそ、
“固定化したルール”ではなく、
“変化に合わせて柔軟に整える”ことが大切。
今日の体調を見て、明日の食事を選ぶ。
その積み重ねが「整った体」をつくります。
まとめ
・SNSの情報はヒントであって、答えではない。
・「正しい」より「自分に合っているか」で判断する。
・食後・翌朝・継続性、この3つを観察する。
・食事はデータではなく感覚でチューニングするもの。
あなたの正解は、検索ではなく“体の中”にあります。
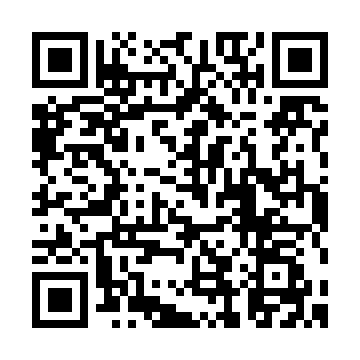 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →