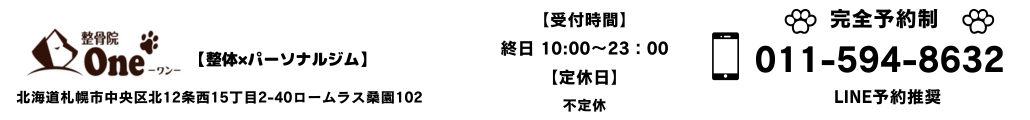孤食と栄養の関係
―「ひとりで食べる」が、体にも心にも与える影響とは ―
こんにちは、犬山和也です。
ちなみに僕は、ひとりで食べるご飯だと8割の確率で“立って”済ませます。
本当は座ってゆっくり味わいたい。わかってるけど、気づいたら…ね。
誰かと一緒に食べる時間が減ってきている現代。
特に大人になると、「一人で食べる」ことが日常になっている人も多いのではないでしょうか。
孤食は必ずしも悪ではないけれど、
続くことで栄養バランスや心の状態にじわじわと影響を与えていくものです。
「栄養が足りていない」だけじゃない
孤食がもたらす影響で一番見落とされやすいのが、
“何を食べるか”の選択が雑になりやすいことです。
・誰かに見せるわけでもない
・献立を考えるのが面倒
・自分のことは後回しにしてしまう
その結果、「とりあえず炭水化物だけ」や「野菜を全く取らない」といった
栄養の偏りや不足が慢性化してしまいます。
ひとりごはんがもたらす“気づかない変化”
孤食には、以下のような影響が報告されています。
・野菜やたんぱく質の摂取量が低下しやすい
・加工食品・冷凍食品の比率が上がりやすい
・噛む回数が減り、消化吸収が悪化する
・満足感や食への楽しみが薄れる
・会話がないことで副交感神経が働きにくく、緊張状態が続きやすい
食事は「栄養」だけでなく「リズム」や「安心感」ももたらす行為。
孤食が続くと、食そのものが“義務”や“作業”になってしまうこともあるのです。
なぜ孤食で「太る人」と「痩せすぎる人」が出るのか
おもしろいことに、孤食が続くと
太る人と、反対に体重が落ちすぎる人に二極化する傾向があります。
・人目がないから「ながら食べ」「過食」になってしまうタイプ
・食事の優先順位が下がって「量が食べられない」タイプ
どちらも「満たされない」という心理的背景を抱えたまま、
身体の状態が乱れていきます。
「孤食をやめよう」とは言いません
生活リズム、仕事、環境。
誰もがいつでも一緒に食べられるわけではないし、
一人の時間を大切にしたい人もいます。
だからこそ、「孤食=悪」ではなく
“孤食になりやすい時期”にどう整えるかが大切です。
孤食を続けるときの工夫
・タンパク質+野菜は必ずセットにする(丼+サラダなど)
・冷凍野菜やカット野菜を活用してもOK
・たまには「食卓に箸置き」を置いてみる
・テレビを消して、10分だけ“自分と向き合って”食べる
・週1回は「誰かと一緒に食べる」予定をつくる(オンラインも含む)
食事は、自分に対する“思いやり”を可視化する時間でもあります。
最後に
「誰かと一緒に食べる食事」は、栄養面だけではなく
心の健康や、自律神経の安定にも関係しています。
でも現実には、すべての食事をそうすることは難しい。
だからこそ、孤食でも自分の体を大切に扱う工夫が必要です。
今日の食事は、あなたの体と心をどう扱ったかの“結果”です。
気負わず、でも少しだけ丁寧に。
それだけで、体調も、気分も、少しずつ変わっていきます。
公式LINE
https://lin.ee/O8uK5K
有料note
https://note.com/kazu20271803
X(旧Twitter)
https://twitter.com/OneOneStep1
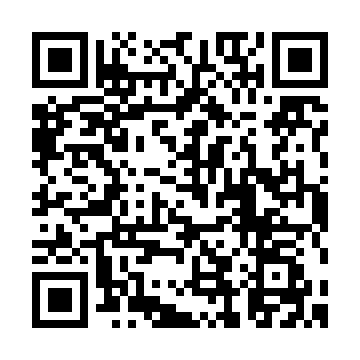 今すぐLINEで体験予約 →
今すぐLINEで体験予約 →